
ブログBLOG
お正月にお餅はどのくらい食べますか?
2023年12月25日:管理栄養士
こんにちは。管理栄養士の前田です。
これから不定期で栄養に関する情報をお届けできたらいいなと思っています(*^-^*)
もうすぐお正月という事で、本日は「お餅」についてお話したいと思います♪
年末年始に食べる機会の増えるお餅ですが、お米から作られているためエネルギー量・糖質量の多い食品となっています。
ごはん茶碗1杯分(150g)のエネルギー量に最も近いのは何個の角餅(角餅1個=55g)だと思いますか?
① 1個
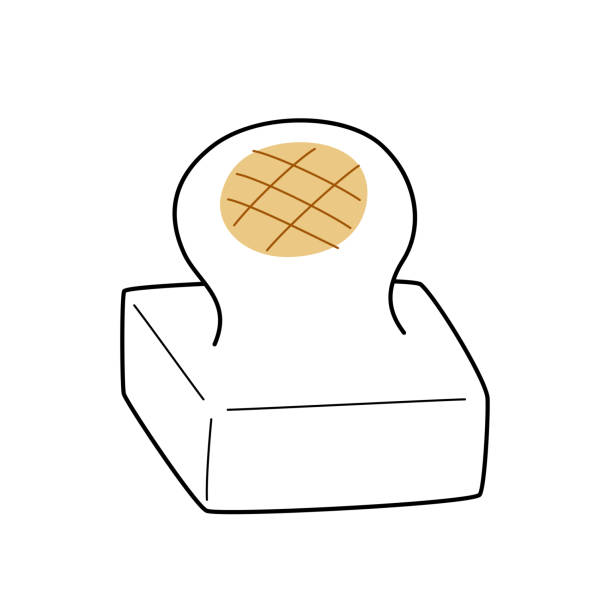
② 2個
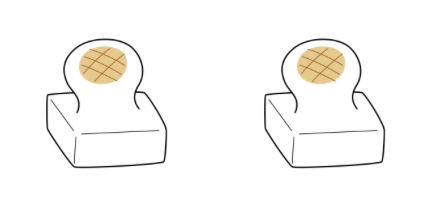
③ 3個
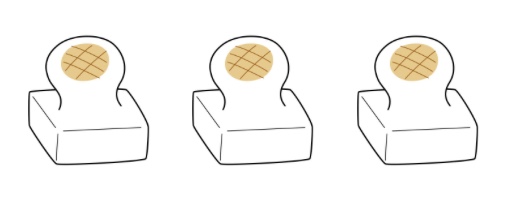
皆さんはわかりましたか?
正解は「 ②2個 」です。
女性茶碗1杯のごはん(白米)150gは252kcal(糖質53.7g)です。
角餅1個(55g)
・・・129kcal(糖質27.6g)
角餅2個(110g)
・・・258kcal(糖質55.2g)
角餅3個(165g)
・・・387kcal(糖質82.8g)
このように角餅2個分がごはん1杯分(150g)に相当します。
1回に食べる角餅は2個までにして、ごはん(白米)の代わりとして食べましょう。
お餅は糖質を多く含むため血糖値を素早く上昇させます。
お餅を食べるときは先におかずを食べるのがおすすめです。
おかずのたんぱく質や食物繊維が急激な血糖上昇を緩やかにしてくれます。
またお正月に食べられるお雑煮は具沢山にすると野菜も摂取できるのでおすすめです。
汁は控えめし、是非いろいろな具材でお雑煮を楽しんでみてはいかがですか?
年末年始はついつい食べすぎてしまう方も多いと思いますが、食べ方や食べる量に少し気を付けるだけで血糖値の上がり方も違ってくると思います。
皆様どうぞ良いお年をお迎えください♪
12月2日をもちまして1年が経ちました
2023年12月5日:お知らせ
タイトルの通りではありますが
はやいもので、
2023年12月2日をもちまして開院から丸一年となりました。
通っていただいている患者さんや関係各所の方々、新参者の私達をあたたかく迎えてくださり本当にありがとうございます。
まだまだ至らない部分もありご迷惑をおかけしてしまうことも多々あると思いますが、地域のかかりつけ医として患者さんに最適な治療を考え、安心と信頼に繋げていきたいと考えております。
今後ともスタッフ一同よろしくお願い致します。
栄養相談再開についてのお知らせ
2023年11月21日:管理栄養士
11月27日より、管理栄養士による栄養相談を再開させていただきます。
相談可能日時につきましては、当面の間、
月曜・金曜の午前診療時間内のみ
とさせていただきます。
(糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの方は保険適応で診察と同日に受けることが出来ます。)
基本予約制となっておりますので、ご予約やご質問等ございましたらお気軽に当院までお問い合わせください。
また、栄養相談の内容については過去ブログにも記載がございますので、よろしければこちらも一読いただければと思います。
↓↓↓
http://kashiwa-dmt-clinic.com/_cms/2023/04/17/
2023年11月、12月、2023年1月の診療について
2023年11月8日:お知らせ
今後の臨時休診などの案内をさせていただきます。
11月14日は検査技師不在のため、エコー検査を施行することができません。
同様に、12月1日、2日、27日もエコー施行不可です。
12月9日の診療は完全予約制とさせていただきます。緊急の要件以外はお断りする場合がございますのでご了承下さい。
年末年始は、12月28日から1月4日まで休診とさせていただきます。
その他、検査施行不可な日程などは適宜お知らせいたします。
勝手ではございますが、何卒よろしくお願いいたします。
11月4日土曜日の診療について
2023年11月4日:お知らせ
11月4日土曜日の診療は、「完全予約制」とさせていただきます。
予約枠も全て埋まっているため、基本的に予約なしの方の当日の診察はお受け出来かねます。
申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。
バセドウ病について
2023年10月24日:甲状腺
<バセドウ病とはどのような病気?>
バセドウ病は、本来自分の体を守るはずの免疫(自己免疫)が自分自身の甲状腺を刺激して、甲状腺ホルモンを作り続ける病気です。別名、グレーブス病とも言います。抗TSH受容体抗体(TRAb)や甲状腺刺激抗体(TSAb)という自己抗体により甲状腺機能が亢進し、全身に様々な甲状腺ホルモン過剰による症状(甲状腺中毒症)を引き起こす、甲状腺機能亢進症の代表的な病気です。
<症状>

代謝をつかさどる甲状腺ホルモンや、交感神経系のカテコールアミンが過剰になるため、典型的には、甲状腺腫大、頻脈、眼球突出が代表的な症状です。その他、体重減少、指の震え、暑がり、汗かき、疲れやすい、軟便・下痢、筋力低下、イライラや落ち着きのなさが生じることもあります。女性では生理が止まることがあります。甲状腺は全体的に大きく腫れてきます。眼球突出に代表される眼の症状は「バセドウ眼症」とも呼ばれ、バセドウ病に特徴的な症状です。眼症は眼科受診を勧めております。
<原因は?>
自己抗体ができる原因ははっきり分かっておりませんが、遺伝的に自己免疫を起こしやすい体質をもっており、その遺伝的要因に加えて、出産や大きなストレス、感染症などの環境的要因が加わって発病してくると考えられています。
<治療は?>
第一選択は薬物療法になります。薬の重大な副作用が起こったり、2年程度薬物療法を行っても安定しない場合は、アイソトープ(放射性同位元素)療法や手術療法を検討します。
薬物療法の第一選択薬はメルカゾール(チアマゾール)です。副作用で使えない場合や妊娠初期(催奇形性が報告されています)はプロパジール(プロピルチオウラシル)を使用します。どちらも服用開始から2~3か月で副作用が出やすいため、その間は2週間毎の採血フォローが必要です。その後も甲状腺ホルモンが安定していれば、1か月毎程度の通院で薬を減らしていきます。薬が少なくなり、甲状腺ホルモンや自己抗体が正常化して3~6か月経過すれば、休薬(内服をやめる)を検討できます。ただし、休薬後も再燃する可能性があるため、定期検査が必要です。
<日常生活、食事などの注意>
一番大事なのは抗甲状腺薬を忘れずに内服することです。改善傾向でも3~4日飲み忘れると急に悪化することがあります。喫煙は、甲状腺ホルモンや眼症を悪化させるため、禁煙を勧めます。運動は、甲状腺ホルモンが高い間は疲れやすく心臓に負担がかかるため、激しい運動は控えて下さい。甲状腺機能が落ち着いてきたら体調に応じて軽い運動から始め、無理はしないで下さい。ヨウ素(ヨード)の摂取は、あまり神経質になる必要はありません。
<妊娠予定の女性の方へ>
甲状腺ホルモンが高い状態での妊娠は母体のリスクになり、胎児にも甲状腺機能亢進症を引き起こす可能性があります。甲状腺ホルモンや 自己抗体が安定していれば妊娠・出産は可能であり、一般的には妊娠中は甲状腺機能亢進症が落ち着く場合が多いです。ただし、メルカゾール使用の場合は妊娠初期に使用しない方が無難であり、プロパジールへの変更などが必要なため、妊娠を計画した時点や妊娠が分かった時点で早めに当院にご相談ください。
↓上記の内容をpdfで1枚にまとめたものを下記からダウンロードもできます。
2023年度インフルエンザウイルスワクチン接種についてのご案内
2023年9月19日:予防接種・ワクチン
当院での2023年度のインフルエンザウイルス予防接種の開始予定日は10/23(月)〜となります。
※10月6日以下記事更新済み(受診歴のない方の予約について更新箇所あります)
※11月6日更新:WEB予約枠を開放いたしました。インフルエンザワクチン接種のみの方は、以下の注意事項をよく読み、WEB予約をご利用下さい。
◇予約開始日
・かかりつけの方→9月11日より予約開始 現在受付中
・受診歴のない方→10月11日水曜日より予約受付開始 現在受付中
※当院のワクチン接種は、年齢15歳(高校生)以上の方に限らせていただいております。
◇接種開始日 10/23(月)〜
◇接種終了日 2024年1月31日
◇費用
・一般(自費) 3500円(税込)
・柏市高齢者助成利用 1500円(税込)
※助成対象詳細については柏市のホームページをご確認ください。
https://www.city.kashiwa.lg.jp/kenkozoshin/hokennenkin/kenshin/yobousessyu.html
◇予約方法
電話または来院時に直接ご相談ください
※11月6日からWEB予約も開始いたしました。インフルワクチン接種のみご希望の方は、WEB予約から「インフルワクチンのみWEB」の枠で予約をお願い致します。
※診察と同日の接種も可能ですが、診察枠の予約も必要であるため、こちらの枠は取らずに事前に電話していただくか来院時にご相談下さい。
◇予診票
・一般(全額自費)の方→来院時にあらかじめご記入いただいた予診票をお持ちいただくと、院内の滞在時間を短くすることができます。
↓予診票
・柏市高齢者助成利用の方→当日専用の用紙をお渡し致しますので、当日来院後ご記入ください。
メーカー側からは今年度のインフルエンザウイルスワクチンはある程度潤沢に在庫があり、当院も数は確保できる予定と聞いておりますが、在庫や予約枠がなくなる可能性もありますので必ず打たれる方はお早めに予約御検討下さい。
※2024年1月10日更新:当院では2023年度の接種を2024年1月31日で終了させていただきます。
2024年度は2024年10月頃からの予定ですが、また時期になりましたらHPでご案内いたします。
新型コロナウイルスワクチン2023年秋接種開始について
2023年9月20日から全国的に接種開始予定のファイザー製新型コロナウイルスのオミクロン株(XBB.1.5)に対応した1価ワクチンの接種を当院でも取り扱うことになりました。
(去年のBA.1の1価ワクチンやBA.4.5の2価ワクチンもオミクロン株対応でしたが、今回のほうが新たな変異株に対応しています)
当院では、2023年9月27日から接種開始となります。
しかし今のところ当院への供給量はとても少なく、毎週1バイアル(6人分)ずつしか配送されず、1度開けると24時間以内に使用しないとダメなので、同じ日で最大6人までとなっております。
ですので当院では、まずは接種日は水曜日のみとし、かかりつけのみ接種可能とします。
※かかりつけとは、この場合は1度でも当院受診したことがある方とします。
現在、3/30土曜日の予約を受け付けております。これが無料では最後のご案内となります。
※3月18日更新:3/30土曜日の予約枠を追加いたしました。土曜日は11時までにご来院ください。こちらの枠で無料接種期間内の当院での接種は終了です。
いずれもかかりつけ関係なく予約をお取りいただけます。
今のところ今年度(2024年3月まで)で新型コロナワクチンの無料接種が終了予定となっております。是非無料の期間内での接種をご検討下さい!
注意事項
・接種券必要(市によってスケジュールなど違う。柏市は申請無しで対象者に順次発送)
・今までで2回の接種を終えている(実質今回が3回目以降の方)
・前回の新型コロナウイルスワクチン接種から3か月以上経過している
・他のワクチン(インフルエンザワクチン以外)と前後2週間空ける
・当院では15歳(高校生)以上のみとさせていただいております。
・予約日の時間指定はありませんが、午前は11時30分まで、午後は17時までに来院をお願い致します。
診察と同日接種も可能です。※土曜日の場合は、診療が午前のみのため11時までにご来院ください。
基本的に電話か直接受付窓口でのみの完全予約制とさせていただきますので、予約をご希望の方はお電話か来院時にご相談ください。
申し訳ございませんが、当院への供給量や接種日など制限があるため、予約が埋まってたり指定日が難しいようであれば他院での接種を御検討下さい。
今のところ無料接種期間は2024年3月31日までとなっております。お早めの接種をご検討ください。
※3月18日更新:3/30土曜日の予約枠を追加いたしました。土曜日は11時までにご来院ください。こちらの枠で無料接種期間内の当院での接種は終了です。
いずれもかかりつけ関係なく予約をお取りできますので、新規の方も接種ご検討下さい。
橋本病について
2023年8月23日:甲状腺
<橋本病とはどのような病気?>
橋本病は、本来自分の体を守るはずの免疫(自己免疫)が自分自身の甲状腺に反応して、甲状腺に慢性の炎症を起こす病気です。別名、慢性甲状腺炎とも言います。橋本病の自己抗体は、抗サイログロブリン抗体か抗TPO抗体であり、どちらか一方でも陽性であれば橋本病(疑い)の診断となります。

この慢性的な炎症によって、甲状腺組織が少しずつ破壊されていき、甲状腺ホルモンが作られにくくなって甲状腺機能低下症や甲状腺腫大が生じます。
<原因は?>
自己抗体ができる原因ははっきり分かっておりませんが、遺伝的に自己免疫を起こしやすい体質をもっており、その遺伝的要因に加えて、出産や大きなストレス、感染症などの環境的要因が加わって発病してくると考えられています。
<治療は?>
・甲状腺機能が低下している場合→甲状腺ホルモン剤(チラーヂンS:レボチロキシン)を内服して機能を正常に保ちます。慢性的に低下している場合は一生涯内服を続けることも多いです。
・甲状腺機能正常の場合→甲状腺が腫れてくるだけでほとんどの場合は症状もなく、治療も必要ありません。ただ、将来的に甲状腺機能低下症になる可能性のある病気なので経過観察は必要です。
機能正常の橋本病の方を5年間観察すると、約30%の方で何らかの機能異常(ホルモン低下や上昇など)がみられますが、その多くは無痛性甲状腺炎など一過性の異常です。
一生のうちに治療が必要なまでに甲状腺機能が低下するのは10~30%程度と言われておりますが、いつなるかは分かっていません。
甲状腺機能低下症は、軽度であれば明らかな自覚症状は現れませんが、放置しておくと動脈硬化などの危険因子となるため、無症状でも6ヶ月~1年毎の甲状腺ホルモン採血をお勧めしています。
もちろん、明らかな甲状腺機能低下症が起こると、寒がり、便秘、体重増加、むくみなどの症状が現れるので、その際は早めに受診してください。
<食事、日常生活での注意>
ヨウ素(ヨード)を多く含む昆布などの海藻類を多く取ったり、イソジンうがいを連用したりすると甲状腺機能が低下する可能性がありますので、過剰摂取は気をつけてほしいですが、絶対に少しでも摂ってはいけないわけではなく、あまり神経質になる必要はありません。それ以外に日常生活での注意はありませんので、特に活動制限などは必要ありません。
<妊娠予定の女性の方へ>
妊娠中、軽度の甲状腺機能低下でも流産しやすくなったり、胎児の成長に影響する可能性があります。橋本病の妊婦は普段の甲状腺機能が正常でも、妊娠すると低下しやすいので、妊娠前後で甲状腺機能を確認する必要があります。できれば妊娠を計画した時点や妊娠が分かった時点で再度甲状腺機能は調べておいた方が良いので、当院にご相談ください。
↓上記の内容をpdfで1枚にまとめたものを下記からダウンロードもできます。
栄養相談休止のお知らせ
2023年8月15日:管理栄養士
皆様
平素お世話になっております。
現在当院では、管理栄養士不在につき栄養相談を休止とさせていただいております。
再開は11月頃を予定しておりますが、その間栄養相談ご希望の方にはご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。
詳しい日程が決まりましたらまたアナウンスさせていただきますので、
ご理解の程よろしくお願い致します。
